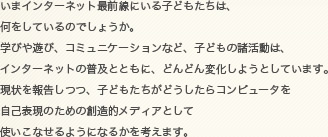本コンテンツは岩波書店 (1997/07)より発刊された「インターネットの子どもたち (今ここに生きる子ども) 」の内容を掲載しております。
掲載内容は執筆された時代背景を考慮し、書籍発行当時のままになっております。
コンテンツの利用・閲覧に関してはこちらをご覧下さい。
インターネットの可能性
協調問題解決過程を解明する

いくつかの考え方を見てきました。今ネットワーク化がまさに進みつつある世界に生きて働いている一人の人間として、考えていることをもう一度まとめてみます。
まず、ものを考えるという作業はふつう一人でするものだと思われていますが、人は、どこまで一人で考えられるものなのでしょうか? 一人では考えにくいとしたら、どういう準備をしておいて、どういう他人とならうまく考えられるものなのでしょうか? もう一つ付け加えるなら、人はほんとうに、他人に自分の話を聞いてもらいたい(別の言い方をすれば、自分自身が情報発信者になりたい)と思っているのでしょうか?
認知科学といわれる私の研究領域で、ここしばらく、協調問題解決過程の解明というテーマがはやっています。最近人気のある研究を一つ紹介すると、ダンバーという比較的若手の研究者が、四つの分子生物学の研究チームの協調問題解決過程を一年間観察して、どういう条件のチームがどういう成果を出したかを分析したというものがあります。心理実験のように最初からいろいろ条件を分けてその差を見たというものではなくて、たまたま四つ選んで一年間付き合って見たら、そのうち二つはけっこういい線をいく成果を上げたのに、ほかの二つはそうでもなかったという事態にめぐり合いました。そこで、では何が理由でこの成功不成功が分かれてきたのか分析できるのではないか、という方法論的にもかなり斬新かつ大胆な研究です。
こういう研究でデータになるのは、毎週の研究チームのミーティングのビデオ記録、ミーティング用に用意されたさまざまな資料、チームのメンバーが書いた研究計画書や論文の原稿、よそへ出かけて行ってした講演とその準備に使われた資料、メンバーへのインタヴュー結果などなど、多彩で膨大な言語行動データです。この膨大なデータから、科学者がいったいどうやって仮説を立て直したり、新しい理論を見つけ出したりするかを探り、そのモデルをつくるのです。高度に探索的、主観的、大胆かつ創造的な研究法であるわけで、私には典型的な認知科学の研究に見えます。授業記録を分析して子どもが何を学んだのか考えていこうという時に私たちが使う方法とも似ています。
これまでダンバーがあちこちのシンポジウムなどで断片的に発表してきているところを見ると、結果は案外常識的なものが多いようです。たとえば、「議論ではアナロジーが多用されるが、現場の研究者がよく使うアナロジーは、分子構造を太陽系にたとえるといったドラマティックなものではなくて、新しい分子構造を推定するのに最近発表された論文から似たような構造の分子を探してきてそれとの異同を探るといった地味なものだ」とか、「考えるときに図やグラフが多用される」とか、「権威主義的なリーダーがいて全体がよくまとまっているように見えるチームよりも、メンバー同士がより対等で構造的には少々不安定に見えるチームで実はより大きな成果が上がっている」とか、「実験をしてその結果が予想外だったとき、どうやったら予想通りの結果が出たはずかという方向で検討していくチームと、その予想外の結果そのものから何か新しい発想が生まれないかという方向で検討していくチームがあり、今回の観察ではこの後者のほうがより創造的だった」とかです。

また、彼によると、このような現場の研究はそのほとんどが集団による問題解決過程とみなせるといいます。そこでは、まず一人が公開で普通の推論をやります。するとその結果がほかの人のインプットになって今度はその人が別の推論をする・・・・・・と、こういう推論の連鎖がみんなの目に見える形で行われ、そのやり取りの間で、問題の表現のされ方、表象が変わります。そのようにして起きる表象の変化が新しい仮説を生みます。情報がいつ誰に渡るかは、個人やグループがその場その場で何をしようとしているか、その目的、および基礎的な知識の共有度によるのだといいます。
私自身、二人の人が「ミシンの縫目はどうやってできるのか」という少々浮世離れした問題をじっくり解いてくれる過程を分析した経験があり、似たような現象を観察してきています。そこで私が見つけたのは、実は、二人が一緒に考えるといっても、一人一人の考えはそれぞれの個人のもの以上に融合したりはしない、という事実でした。二人で一緒に考えても、他人の到達した解答をもう一人が途中から自分のものにするなどということはほとんど起きません。では、一緒に考えることに利点がないのかというとそうではなくて、他人はこちらの考えを素直にすぐ受け入れてくれないので、その引っかかりが自分で自分の考えを再吟味する契機として役に立つようです。
協調問題解決の少なくとも一つの利点は、自分一人で考えていれば納得してしまいそうなことに対して、そこに至る論旨の流れやこまかなステップ一つ一つについてとりあえず異議を唱える他人がいることであるらしいのです。だから、お互い相手の試行錯誤の経緯が見えやすくて、互いにちょっかいをだしやすいようなお膳立てができているほうが協調作業の利点も出てきやすいといえます。第二章で人は他人に分かってもらおうとして自分自身の考えを深めてゆく傾向があるらしいと書いた根拠はこのあたりにあります。お互い結果だけを持ち寄って、「いや、いずこも努力しておりますな」というエール交換だけに終始するような交流であれば、他人の果たす役割は限られてくると考えたほうがいいでしょう。
一緒に考えてくれる仲間を探す

考えるという活動は、何が当面分かっていなくてこれから何について分かることが大事かが見えてくるところまで自分を追い詰めることとほぼ同義ですから、しつこさが大事になります。ちょっと考えてああそうか、という考えはむしろ危なかったりします。じっくり吟味して初めて見えてくるものに価値があることが多いといえます。
「じっくり吟味」はたいてい一人でやるものです。
けれど、上に挙げたような研究のエピソードからみると、人は確かに一人で考え続けるということはむずかしそうです。そもそも「誰か成果を喜んでくれる他人がいなければ考える気など起こらないのが人間だ」という科学史研究家もいるくらいですから。だから、その意味では、人は一人では考えないのでしょう。一緒に考えてくれる仲間を探すこと、そのためのインターネット、というアプローチが有望視される大本はこんなところにあるのではないでしょうか。
しかし、このロジックで行くと、普通は一人でやるはずの自分の考えについての吟味を、一緒にやってくれる人、それもじっくり付き合ってくれる人を探すわけですから、ただ運を天に任せていたのでは効率は悪いはずです。北米のプロジェクトのいくつかに共通してみられた一人一人の考え方を他の人と共有するためのノートや、自分の考え方の根拠やまだ分かっていないところを明示させるための仕組みは、この「じっくり吟味」に他人を巻き込むための仕掛けなのだと考えられます。
話題をしぼって話をして、互いに分かり合うための協調活動を通してそれぞれ自分の知らなかったことを確認したり、自分の分かり方を深めたり、さらには新しい考え方を拓いて行くという、いわば「不自然な」作業が起きるためには、一度その場に参加する一人一人が、何を知っていて、何を正しいと思っていて、それを根拠にどんな方向に考えを発展させようとしているのか、その思考のプロセスそのものを互いに見える形で共有することから始める必要があります。そういう媒体として使えるメドが立つとき、インターネットの上に作り出される世界が考える力や学ぶ力に結び付く道具にもなりうるということなのではないでしょうか。
情報発信者の二極

さらにもう一つ、考えておきたいことがあります。インターネットなど表現の舞台がそろってくると、人はみな自分を表現したくなるものだと言われているようですが、この表現とは具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。この本のここまでの議論で考えてきた情報発信はほとんどの場合「私はこう考えます、ところであなたは?」とか「あなたはそう考えるかもしれませんが私は違ってこうです」とかいう形で自分の考えを相手と対立させることを意味します。考えるというプロセスに、ここで見てきたような互いの知識の共有や見直しのプロセスが含まれているのだとすると、そのもっとも単純な帰結として、それは自分と他人との違いをあらわにすることでもありますから、自分の考えを他人に公開するとそれだけ攻撃される可能性も高くなる、ということがあります。この他人からの攻撃を甘んじて受ける覚悟をしてまで、人というものはほんとうに自分自身が情報発信者になりたいと思っているものなのでしょうか。
私の勤務する学部ではかなりの数の授業にそれ用のニュースグループが作られており、そこで授業外の意見交換や学習活動が行われています。このような環境での学生の反応は少なくとも二種類あります。一つは、「先生以外の他人の意見が読めておもしろい」「自分と同じようなことを考えている人がいることが分かってうれしい」というものであり、もう一 つは、「何か発言するとそれに異を唱える奴がいて、なんか気に食わない、気分が悪い、怖い、あまりニュースはやりたくない」というものです。
この後者は、自分の意見が否定されるのがいや、というだけではありません。誰か名前も知らない他人の意見が、顔も知らない別の他人に非難されるのは見るのすらいや、という反応があります。こういう傾向が強いタイプの学生がインターネット活動がきらいかというとそんなことはなくて、あちこち出かけて行って情報を集めてくるタイプであることはありえます。さらにまったく自分から情報発信しないというのではなくて、自分のホームページをきれいに作ったりするタイプであることもあります。
「来て見てくれる」ならいいけれど、しかし自分から出かけて行って自分を誇示してくる、ましてやケンカを売ってくるようなことはしませんよ、というタイプであるように見えます。情報の発信の仕方にはいくつかのタイプがあると考えたほうがよさそうです。
今のインターネットは、この後者のタイプの情報発信者が居心地のいい発信場所を見つけてどんどん増えていっている、そういう意味でも新奇なメディアなのではないでしょうか。積極的に議論をふっかけるタイプではなくても発信は発信であり、その発信のゆえに私たちが手にできる外化された知識の量が日々爆発的に増えていることだけは確かであるようです。
けれど、わたしたちは、こういう大量情報の扱い方に慣れてはいません。このタイプの発信する情報がほんとうにたくさんになったとき、そこに外化されている情報をどうやってここで考えてきたような協調問題解決用の吟味の枠組みに取り込んでいったらいいのかはまだまったく分かっていないのです。情報源の多様性をそれはそれとして尊重しながらかつ協調的に共同で問題解決しながら学ぶ、といったことが可能なのかどうか、可能だとしたらどんな形で可能なのか、これからの大事な研究テーマの一つだと思っています。
未知を創造する力

ものを知っていることそのものは、どこに行ったらどのようなことを知ることができるかを知っていること、と比較して重要ではなくなってくるかもしれません。公式を当てはめて問題を解けることよりは、問題を解くためにはそもそも何をしたらよさそうかを知っていること、とにかく問題に取り組めることのほうが貴重だと考えられるようになりそうです。さらに言うなら、与えられた問題が解けることよりも、何が問題なのかを見つけ出すこと、問題そのものを作り出すことができなければ、次の世代を生き延びていけなくなるかもしれないのです。教育は、どこかで、既知ではなくて未知を創造する力と結び付いていかなくてはならないのでしょう。そういう未知の探究のために既知の情報をできるだけ探しやすく提供すること、それがこれからのインターネットづくりの指針の一つだろうと思います。
インターネットは、今ここに、価値を試されるもの、情報を扱うための道具として私たちの手元にあります。これを、今あるこのままの形でこれがどう使えるかを議論し、検討する、という発想は、どこか違うのではないでしょうか。インターネットをどうしたいのか、どう作っていくのか、がそもそも問題なのではないでしょうか。ちょうど、今この私たちを取り巻く社会が、私たちに絶大な影響を与えるものでありながら反面それ自身私たちが作り上げてきたものであるのと同じように、ネットワークも、目をつぶってもなくなりはしないし、私たちの生活の仕方や、教え方、学び方、ものの考え方に影響を与える存在として、私たち自身が作っていくことになるでしょう。
ネットワークをそういうものとして捉えたときに、インターネットと子どもたちの関係をどう考えるかという問題は、私たち自身が子どもたちと一緒にこの社会をどう作り上げていこうとしているのかという問題と同じです。私たち自身が子どもたちと一緒に作り育てていくものとしてのインターネット、そういう立場からネットワークのこれからを考えていきたいと思います。