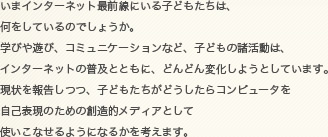本コンテンツは岩波書店 (1997/07)より発刊された「インターネットの子どもたち (今ここに生きる子ども) 」の内容を掲載しております。
掲載内容は執筆された時代背景を考慮し、書籍発行当時のままになっております。
コンテンツの利用・閲覧に関してはこちらをご覧下さい。
1.教室の壁を壊すこころみ
先生の知らない情報が飛び込んでくるとき

インターネットを利用した教室活動というものは、「教室の中に限定された学びは教室の外で役に立たない」という認知研究への一つの回答として考えることができるでしょう。教室のコンピュータがネットワークにつながると、マウスのクリック一つでいろいろな情報が手に入ります。そういう様子を初めて見たとき、子どもたちはやっぱりびっくりしたり喜んだりします。そうやってびっくりしたり喜んだりしている子どもたちの後ろ側で見ている先生たちが、もっとびっくりしている場合もあります。
何にびっくりしているのか、ネットワークを使う子どもたちを見て先生方がどんな予感を持つかを想像してみると(その予感の中には不安も含まれるのではないかと思うのですが)、こうやって子どもたちがいろいろな情報に直接触れることができるようになると、そのことについて教えるための準備はいつしたらいいのかが分からなくなることであるかもしれません。
子どもたちのほうが先生の知らない情報を先に手に入れる、そういう状況がネットワーク化された教室の中ではどんどん起こってくるでしょう。そうなると、先生たちに問われるのは、前もってよく準備をして子どもたちに分かりやすく話をする能力ではなくて、わけの分からない情報がたくさん教室の中に飛び込んできたときに、それを整理して、その中から知っておいたほうが便利そうなこと、分かってうれしいことを抜き出してみせる、そんな能力になっていく可能性があります。
これまでの教師教育の中では、こういういわゆる情報収集・整理・編集能力を身につけるための努力はあまり意識的には推奨されてこなかったのではないでしょうか。そういう機会がそもそもなかった、と言えるかもしれません。いまのところは、教育学部の授業の中でさえ、学生自身がネットワークでいろいろな情報を集めて、それを整理して、新しい何かを見つけるというような課題が日常的に取り上げられるようになっているところは、あったとしてもほんの少数でしょう。しかし教室には、実際すでに一〇〇校プロジェクトを始めとして、どんどんネットワークが入ってきています。先生たちを育てる教育の仕方が変わっていくのももうすぐだろうと思います。
先生たちのネットワーク
教室のコンピュータがネットワークで世界中の情報源につながったら、先生たちだってお互いに「つながることができ」ます。「ネットを使ったらこんなことが起きた」「こんな教材が欲しいが誰かどこにあるか知らないか」「ネットを使ってこういう授業をしたい、協力してくれる人はいないか」といったやり取りが、今もうすでにネットの上を行ったり来たりしています。小学校から大学院にいたるまでのどのレベルでも、自分たちの授業のために使っている教材や教案、生徒同士の議論の様子などを、どこまで見せるかの差こそあれ公開しているところがたくさんあります。大学などでは、それが実際高校生に向けての大学の宣伝になるから、公開に積極的にならざるをえません。学びは、先生たちからだって、変わる可能性があるのです。
この章では、実際インターネットを使って教授をしてみようかということになった時どんな教え方をすることになるのかを、第二章で見てきたような知の把え方の変化に絡めて考えてみることにします。なかには、これまで「教え」や「学び」について常識だと考えられてきたことを見直さなければならないような話も出てくるように思います。
2.学ぶ順序を自分が決める
新しい二つの考え方

ネットワークの教育利用について、「いつでもどこでも好きなときに好きな人が好きなことを学べる」というキャッチフレーズがあります。学びが学校だけでなされるものではなく、これからは、必要なときに必要な人が必要なことを学べばいいのだ、というわけです。これはけっこう誰でもが賛成するキャッチフレーズで、できる範囲でなるべくそうすればいいのではないかと考えている人が多いかもしれません。私もそう考えているのですが、しかしここには、これまでの日本の学校教育のやり方とは大きく違う考え方が二つ入っているようです。
その一つは、「みんなが同じことを学ばなくてもよい」という考え方で、もう一つは、「ものごとを学ぶのに決められた順序以外の順序で学んでもよい」という考え方です。これらは、どちらも真面目に考えるとこれまでの学校教育でなされてきたものの学び方とは極端に違うものの考え方です。それぞれもう少し詳しく説明してみましょう。
「みんなが同じことを学ばなくてもいい」という考え方
前者の、「みんなが同じことを学ばなくてもよい」という考え方については少なくとも額面としては納得する方が多いのではないでしょうか。それはそうだろう、現実に算数が好きな子も国語が好きな子もいるんだから、とおっしゃるかもしれません。しかし、今の日本の学校教育はこういう考え方で成り立ってはいません。大学ですらそうです。世界史は勉強するけれど日本史はまったくやらないとか、図画工作はやるけれど体育はやらない、という選択はこれまでの学校教育ではなかった発想です。しかし、好きなことをじっくり時間をかけて勉強しようと思ったら、それしかできなくなることは十分ありうることでしょう。
少なくとも、人の授業を聞くよりはネットに張り付いて自分で資料を集めて読むほうがおもしろいという学生が出てもさほど不思議ではないでしょう。またこのようにして「世界史を学ぶ」と、世界史と呼ばれる分野のなかでも高校の三年間かけてある特定の(特殊な、かもしれない)テーマ、たとえばビザンチンの美術様式についてしか学べなかったなどということが起きるかもしれません。
そのことを認めたうえで、「いやあやっぱり世界史ちゃんとやるなら、北京原人からヒトラーまで一応ある程度やっておく必要があるんじゃないの?」とするか、世界史が好きならそのなかの一テーマをとことん追求して、そのテーマに関連してくるところはそこだけ押さえて、最終的には特定の切り口から歴史を見る方法を探ればいいと考えるかには大きな違いがあります。
ネットワークを利用して、みずから問題を設定して学ぼうというやり方は、自分が調べてみたいことについて十分時間をかけなければ成り立たないやり方ですから、当然他のことに割ける時間は減るでしょう。つまり、「ネットワークを使って自分で情報収集しながら学ぶ」ことがいいことだと言う時、それは極端に言うと、ビザンチンの美術様式だけでもそこがしっかり分かっているなら大学入試の終わりと一緒に消え去ってしまう付け焼き刃的な一時的知識よりよっぽどましだ、という意味のことを言っているのに非常に近い、ということを覚悟しておかなければならないのかもしれないのです。
何にせよ一つの領域の知識を身につけるのにかかる時間と知的労力がどのくらいのものかは、これまで不当に低く見積もられてきた可能性があります。ノーマンという人の推測によると、お手玉にしろ一輪車乗りにしろ、心理学にしろ、その道のエキスパートと呼ばれる域の知識、技能を身につけるのに五〇〇〇時間はみておく必要があるのではないかといいます。

お手玉に五〇〇〇時間かけたとき、ほんとうにお手玉〈しか〉できない人間が育つわけではなく、そこまでやった人であれば、お手玉を切り口に「学びとは何か」について語ることができるかもしれないわけで、言い換えれば、お手玉を学んだ結果転移しそうなもの、応用できそうなものはいろいろある可能性はあります。しかし転移する先が、では具体的に何なのかなどというむずかしい問題は、これまでの認知研究ではまだほとんど触れられていません。
これまで私たちが知っていた学校教育ではいろいろなことを万遍なくカバーしようとするわけですから、中高一貫教育といったところで、どれかの教科を一つと考えるにしても、そのどれ一つとっても五〇〇〇時間はおろか一〇〇〇時間かけることすらしてはいません(週三時間かけられる教科があったとして、実質授業ができるのはどう多めに見積もっても三五週でしょうから、一年で一〇五時間、運よく六年間続けられたとして六三〇時間です)。しかもそれで一つの教科全体をカバーするのです。それから考えると、日本中の大人がみんな「高校の生物って何やったっけ?」という状態であったとしても、誰も十分な時間をかけていないのだから、たいして不思議ではないとも言えます。
ある人が、あることについて詳しいというとき、その人がかけている時間はけっして「学校の時間割で割り振られていた時間+その予習復習に費やした時間」では収まりきらないはずです。高校時代にこれはやったな、と思わせる何かを身につけたいと思うなら、もしかしたら、いろいろ万遍なく学ばせることをあきらめて、何か一つ、けれどそれには「できるだけいろいろな角度からいろいろな資料を集めて、専門家の意見も聞きながら」自分で学んでいくしかないでしょう。ネットワークは、専門家に直接話が聞きやすい、とか、根気よく探せば相当量の情報が前より手軽に手にはいる、というような意味で、うまくやればそれができる環境を私たちに提供し始めているように見えます。
「決められた順序以外の順序で学んでもいい」という考え方
もう一つの考え方、ものごとを学ぶのに決められた順序以外の順序で学んでもよいという考え方は、言い換えれば、ものごとを学ぶのに突然むずかしいことから始めるとか、「基礎」を飛び越して「応用」から始めるなどしてもよいという考え方です。誰かが決めたやさしいことからむずかしいことへとか、学びやすいことから学びにくいことへ、などのような一定の順序を踏まなくても学びが成り立つと考えるわけです。
極端に言えば「四則演算を覚える前に突然微分積分から学んでもいいのではないの?」とか、「一とか上とか画数の少ない簡単な漢字から覚えるより、亀とか鼻とかもっと直接表意的で印象に残りやすい漢字から覚えるほうがいいのではないの?」という考え方です。数学、特に高校数学の教え方の研究では、このことがずいぶんと長いあいだ問題になってきました。その結果認められるようになってきたのは、先回の指導要領の改訂に反映されたような現地調達方式と呼ばれる一種の原則で、そこでは数学の世界でも基礎とその応用が完全一次元的な積み上げ方式にはなっていないことが再確認されているようです。
ものごとの教え方を簡単なものから複雑なものへの積み上げ方式にしないほうがよさそうだ、という考え方には大きく言って二つの根拠があります。一つの根拠は、積み上げ方式の背骨に当たるものごとの順序をきちんと決めることがけっこうむずかしい、ということです。これは、世の中で私たちが使っている知識そのものが場に適応的に働くものであって、実はそれほどきちんと段階をなして積み上げられるような部分に分かれていないことを反映しているかもしれません。同時に、もう一つの根拠として、この積み上げ方式は、うまい部分わけの仕方と積み上げ方が分かったとしても、その部分わけや積み上げをやる人が学ぶ人とは違うので、学ぶほうにとってみると、いつ、なぜ、何を学ばなければいけないのかが見えにくくてやりにくい、ということが挙げられるでしょう。
作文を教える側から考えると、いい文が書けるためにはまず字がきちんと書けて、その字をつないで意味の通った文が書けて、その文をつないで一塊の段落が構成できて、それらの段落をつないで文章が作れ、その積み上げできちんと言いたいことの主張ができるというのが一つのものの順序だったとしてみましょう。
こうすると、教え方としてはこのピラミッドを逆にたどって、文章が書けるためには、言いたいことは最後にまとめあげられればよくて、まずは字がきちんと書けないと、ということになります。だから、先生は作文の時間を使って生徒に字の練習をさせるわけです。このとき、先生には、「いい文章を書くためには字がきちんと書けないとね」という具合にその場の作業と将来の目的とのつながりが見えているかもしれませんが、下手をするとこれが見えているのは先生だけということになりかねないでしょう。生徒は「何のためにやるのか分からなくてつまらない」と思いながら字の練習をしているだけになってしまうかもしれません。そうなった時には、生徒にやる気が出なくても、むしろそのほうが自然というものでしょう。

字の練習がおもしろかった、それなりにやる気が出るということはあるかもしれませんが、それならそれでいいのかというとそうでもないでしょう。なぜなら、先ほどの状況論的な解釈を持ち込めば、この場で字の練習がおもしろいということは、教室で字の練習をすること(と、その結果として漢字テストでいい点が取れること、くらいまで入るかもしれません)そのものが目的化していることの表われである可能性が高いからです。だからこそ、先生が目的としていることは、それそのものが生徒の活動目的になるような仕組みが欲しいのです。作文をするなら、「伝えたい相手がいて、伝えたいこと、書きたいことがあって、それをその相手に伝わるように書く」状況が作れることが大事でしょう。そういう、伝えたい相手として先生以外の人を教室に連れ込むためには、ネットワークは分かりやすい手段を提供してくれると思います。
学びの効率ということを考えるとき、現地調達方式がほんとうに能率的かどうかまだ分かってはいません。必要なところはあちこちで同じことを教えるから、一見必ず効率がよくないように見えるはずです。きちんとした比較をするためには、まず、これまでの教え方でほんとうに何がどこまで教えられていたのかを見直してみることが必要になるでしょう。案外「教えた/教えられた」つもりになっていただけ、ということだってあるかもしれません。そのような見直しの上に立って、こんどはほんとうに、ではどうやったら学校を出てからもながいこと実生活に役に立つ知識を身につけることができるのか、それを考えていく必要があるのだと思います。
3.内省から評価へ
CSCLの研究会の発表で
国際的に見たとき、インターネットやマルチメディア技術を利用して教育を改革しようという研究はすでに相当の実績を積み上げてきています。一九九五年一〇月、アメリカでCSCLという研究発表組織が新たに動き出しました。コンピュータを、共同作業としての学びや協調的な学習に役立てるにはどうしたらいいか、その方略や実践について話し合おうという「協調学習のためのコンピュータ支援(Computer Support for Collaborative Learning)」のための研究発表会です。私も行って様子を見てきましたが、第一回目ということもあり、これまで一〇年以上の成果をまとめて発表するようなケースも少なくなくて、熱気と活気の感じられる好スタートだったと思います。次回は一九九七年一二月にトロントで開かれます。
会では当然インターネットを使うとどんな新しい教え方ができるようになるかがさかんに議論されていました。あちこちの研究発表で繰り返し使われていた「はやりことば」に、
- ・authenticity
- ・scaffolding
- ・reflection
がありました。
それぞれ、意訳すれば、「真実性」、「足場かけ」、「再吟味」、とでもいうことになるでしょう。それぞれ先に第二章で説明した知についての新しい見方と密接に関連しています。「はやり」であるだけに人によって使い方も異なります。ですが、大胆にまとめてしまうと、それぞれ次のようなことになります。
まず、真実性を重視するとは、「学校で教えることは、将来ほんとうにその力が必要になる場面で要求される知力、つまり本物の知力とできるだけ同じであるように配慮するといい」ということです。受験用のテクニックではなく将来自分が働く場所でほんとうに役に立つ知力を身につけよう、というスローガンだと考えればよさそうです。これは、もちろん先の状況論的な知の見方、人はその場その場でやるべきことをその場のものや道具や他人を使ってうまく処理しているよという見方と関連しています。
次の足場かけという考え方は、家庭での子育てや職場の新人教育、若手の養成など学校以外の教育場面で知識や技能がどう伝えられていくのかについての観察、分析に基づいて、「なにも始めから全部一人でできる必要はない、手助けしてあげればできることなら、どんどん手助けしてあげてでもできたほうがいい」という考え方です。先に挙げたヴィゴツキーの考え方をもとにしていることが見てとれるでしょう。
だから、教え方の方針としては、「人間誰でも、どこかの時点で人に手伝ってもらってやっとできたことを、いつのまにか一人でできるようになって一人前になるのだ、だから、教育の場ではできるだけうまい手助けの仕方を考えよう」ということになります。
最後のreflectionという用語は、「反射」とか「内省」とも訳されることばで、ここで内的な反省の対象として考えられているのは自分自身の考え方やもののやり方です。ただ、ここでいうreflectionは、内省すればいい、というだけではなくて、自分自身の考え方ややり方を吟味してみて、何がいいのか、どこがもっとよくなりそうか、など作り替える工夫をするところまでを含んで言われることが多いように思います。自分自身に対する批判的思考力、と考えたらよさそうですので、ここでは再吟味と呼んでおきます。
ですから、再吟味を大事にする教育観を言い表わすと、「結果よりも過程が大事、それよりもっと大事なのは過程そのものを自分で振り返って良し悪しを吟味して、もっといいやり方を工夫できる過程」ということになるでしょうか。再吟味が大事だという場合、単に何かができるようになるだけで満足してはいけない、もっといいやり方を自分で考えられるような方略をも身につけてもらわねば、ということになるのです。そのために他人の存在が大事、だからネットワークが再吟味の道具として期待もされているのだという話は第二章で軽く触れた通りです。
知が状況依存的で、共有のメカニズムに支えられて獲得されるものだからこそ、そういう知に対して自覚的に内省し、作り替えて行く努力が大切なのだ、ということになります。その意味でこの内省を重視する立場も知の見直しをへて出てきた考え方だということが分かっていただけると思います。
評価についての考え方も変わる

インターネットの教育利用が盛んになってきたのにつれて、教育評価の考え方そのものも変わらざるをえなくなってきつつあると思います。教育に関する新しいキーワードの最後に挙げた再吟味は、この教育評価の問題にじかにかかわってくるものです。教育の真実性を大事にして、足場をうまくかけながら何か教えるとすると、どこで終わりにしたらいいのかははっきりとは決まってきません。むしろ終わりがないのが本当の姿らしいのです。
教育の究極の目的は、教師ができることを生徒も同じやり方でできるようにすることではおそらくないでしょう。世界は変わっていくのだから、生徒には教師のやり方よりさらにいいやり方を作り出していってもらわなければなりません。ところが、教師が教えられるのは、自分のやり方でしかないから、せめてそれにプラスして「自分のやり方のよくないところを見つけてさらにいいやり方を作り上げていく方法」があるなら、できるだけそれを一緒に教えるようにする必要があります。この「さらにいいやり方を作り上げていく方法」の一つとして期待されているのがまさに再吟味という過程です。
再吟味というのは、自分のやり方を自分であれこれ検討してみること、もっといいやり方はないのか工夫してみること、自分に対して批判的になること、を意味します。当然、自分に対してすら批判的になりましょうということですから、他人のやっていることにあれこれ難癖をつけてあれもだめ、これもだめ、なかでは自分のが一番いいけれどそれでもまだここがだめ、というような批判的・悲観的かつ攻撃的な話になり、これをやり始めるとけっこうしんどいかもしれません。しんどいのだけれど、こういうことを真面目に教育の目標にしてみたらどうなるか、とにかくやってみましょう、というのがスタンスです。
再吟味は、自分で自分のやっていること、認知プロセスに働きかける過程であり、その意味でメタ認知的なプロセスだと言えるでしょう。メタ認知は、最近また認知研究の一つのホットテーマになりつつあるように見えますが、試験的な分類案が出されている程度で、そもそもどういう働きなのか、働くためにどういう条件が必要なのか、どうやったら促進可能か、など詳しいことは分かっていません。
再吟味のプロセスがどういうものかが詳しく分かっていないのですから、その力があるかどうかをどうやって調べるのか、評価の仕方もまだちゃんとは分かっていません。こういうことはいい再吟味を実際数多く体験しているかどうかが問題で、評価の対象となるようなものではないという議論もありえます。
教室で一〇歳の子どもが、「今」再吟味できることが大事と考えられているだけではなくて、その子どもが三〇歳になったときほんとうに社会の現状をよりよく変えていけるような形で働くかどうかが問題なのですから、実時間で研究するためには一セットのデータを取るだけでも二〇年かかる計算になります。気が遠くなるような話ですが、今はそういう試みが本気で取り上げられるようになってきたことを歓迎すべきだと思っています。
会社ベースで行われてきたコンピュータによる協調作業支援システムの開発研究のなかにはこれまでの常識を見直させるようなものも出てきていて、学校への応用を考えると十分刺激的というものも少なくありません。
(余談ですが、アメリカの教育研究者の知人に、「全米統一試験制度」というおよそアメリカらしくないと感じられるプロジェクトに深くかかわっている人がいます。日本を視察し、統一テストの酸いも甘いも十分噛み分けたうえで、それでもアメリカ全土の教育レベルを上げるために良質のテストを作り上げることが必要だという信念の持ち主で、テスト作り、実施の可能性を少しでも多くの州に打診するための政治的バックグラウンド造りから、そういうテストが意味を持つような教育カリキュラムの試作、そのカリキュラムで実際教育できる教師教育のプログラムの開発、教師教育の実施、研究協力校探しなど、とてつもない量の仕事をこなしています。彼女の研究の成果がいつ、どういう形で出るのかをおそるおそる聞いてみたところ、「成果が出るころには私は生きていないわ」とあたりまえのように言われて少々感動した経験があります。私は自分が教育研究にかかわっていると思いながら、十分な再吟味が効いていないのか、ここまで自覚的になることは少ないのですが、教育研究にはこういう側面がほんとうはあるのだろうと思います。)