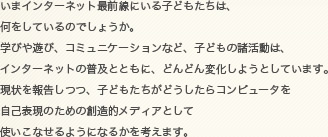本コンテンツは岩波書店 (1997/07)より発刊された「インターネットの子どもたち (今ここに生きる子ども) 」の内容を掲載しております。
掲載内容は執筆された時代背景を考慮し、書籍発行当時のままになっております。
コンテンツの利用・閲覧に関してはこちらをご覧下さい。
1.昔、あるネットワークで起きたこと
ICLNというプロジェクト
第2章で説明してきたような、知に対する考え方の見直しが研究報告としてあらわになってきたのは、約20年ほど前からの話です。そのごく初期から、ネットワークを教育に利用することで学びをうまく状況依存的にすることができるのではないか、という試みはありました。そのような初期のネットワーク利用の1つが、私自身もその一部としてさまざまな体験を積むことになったICLNという名のプロジェクトです。この本の冒頭の南中時プロジェクトも、前章の英語学習の実践も、このICLNでの出来事です。
ICLNは文化間学習ネットワーク(The InterCultural Learning Network)の略で、1984年から1992年ごろまで稼働していました。参加校、参加都市、参加国はその時々で変化しましたが、コアをなしていたのは、カリフォルニア大学サンディエゴ校の教師教育プログラム、イリノイ大学教育学部、ヘブライ大学教育学部(後テル・アビブ大学教育学部)、青山学院女子短期大学の4地点でした。
「ネットワーク」から「教育」へ

始まりのきっかけは、「小学生にちゃんとした読み手のいる場面を作って作文をさせる教育実践にコンピュータが役に立つのではないか」というプロジェクトでした。このとき活動の中心だったのは、主にサンディエゴとフェアバンクス(アラスカ州)で、初めは実はネットワークは使っておらず、フロッピーディスクを郵送でやり取りしていたのです。
その実践のなかで私たちが見たのは、子どもたちが、カリフォルニアの海を知らないアラスカの子どもたちに自分たちの知っていることを知らせようとして推敵を繰り返す姿だったり、相手の文章に理解しにくい部分を見つけて、どうたずねたものか思案に暮れる様子だったり、いろいろ書いているうちに大文字と小文字の使い分けだとか、読みやすい段落の切り方だとかを自然と身につけていく事実だったりしました。
その試みが少しずつ広がって、メキシコの商業学校の生徒たちが参加してきてスペイン語で手紙を送ってくるようになって、ことばの壁をどうしたらいいか悩む自分たち自身の姿を見つけたりもしました。ネットワークが何らかの形で教育にかかわるようになってきたのです。それも教えや学びがどういうものであるべきかを考え直さなければならなくなるような形でかかわってきました。そういう直観を、あの時の経験から得た、と思います。そこで、どんなテーマで、どんな情報がやり取りされ、それを参加した生徒たちがどう受け止めたのか、事実を少し紹介してみます。
さまざまなプロジェクトの成功と失敗
私たちは最初から、ある特定のテーマでの情報のやり取りが大事だと感じていました。知りたいことがあって、それを知るための手段としてネットワークが活用される、という形を実践の基本に置いていたのです。ですから、実践のなかでは、知りたいことはいったい何なのかを決めるまでにずいぶん時間をかけました。時には、先生が 「こういうテーマで情報交換したら」というアイディアを出すことがなかったわけではありませんが、「それもじゃあやりましょう」という学生が国際的にあちこちにいなければ始まらなかったのです。だから、いろんなことを試せましたし、試してみた結果失敗も多かったのですが、多少負け惜しみを言えば、その失敗が私たちに教えてくれたことも多かったような気がします。以下、印象に残っているテーマと、そこで何が起きたのかを並べてみましょう。
1)飲み水はどこからくるのか

これは、カリフォルニアで実際こういう題材で教えなければならない先生が、「教科書にあるこの問題は、教科書にあるから大事なのではなくて、今大人の社会で現実に大切な問題なのですよ」という話をしたくてネットに乗せたのがきっかけでした。
これは、ICLNが本格的に動いた最初のプロジェクトでした。カリフォルニアは、隣のコロラド州から水をもらっており、時々は水が州の間の政治問題化するという場所です。いったん子どもたちの目がそちらを向けば、リアリティには事欠きません。実際聞いてみると、イスラエルには水源がガリラヤ湖1つしかなくて、海水を利用する方法の開発が長いこと国の重要課題だそうです。アラスカはというと、雪と氷がたくさんありそうですが、氷は実はそのまま飲むわけにはいかず、溶かすのにかかる資金が問題になっていることが分かりました。東京は東京で、地面がどんどんアスファルトで舗装されてしまって雨水が土に浸み込まなくなっており、慢性的に水資源が足りません。
情報を集めてみれば、水がありあまっているなんていうところはなかったわけで、その意味ではこのプロジェクトはやってみて大成功でした。それぞれの土地での解決法を子どもたちが調べて交換し、他の土地の解決法が自分たちのところでも役に立たないかを考える、というような活動も起きました。
それぞれの土地からの情報源のなかにはすでに、子どもたち以外の人の参加がかなり重要な役割を果たしています。子どもたちだけで分からないことがあっても、それを補ってくれる人がネットに参加していれば活動はできます。それぞれの教室で、子どもたちはかなり違った活動をしていますから、そのプロセスをお互いに知らせるような仕組みがあったほうがよいことも分かってきました。
テーマが決まっていてこそ子どもたちは情報集めを一生懸命やりますし、もらった結果からものを考えようとするらしい、などと、その後の活動方針のいくつかが、このプロジェクトを通して固まってきました。
2)月の満ち欠け
月の満ち欠けを観察する、というのはどこでもやられている活動でしょう。富山県の小学生がこれをやっていたとき、観察結果からおもしろい仮説を立てた生徒がいました。山手に住む子の観察結果と、町中に住む子の観察結果が微妙に違うから、見る位置によって月の欠け方に違いがあるのではないか、という仮説だったそうです。
この仮説を聞いていた先生が、たまたまICLNのことを思い出したのが運がよかったといえるでしょう。彼から私のところに連絡が入り、子どもたちの仮説では、山手と町中で欠けの見え方が違うくらいだから、イリノイやイェルサレムであれば、片方が半月ならもう片方は満月くらい違うのではないか、ネットの上で10月29日の月の形を教えて欲しいという依頼でした。
結果は、子どもたちにとっては残念なことに、どこの地域で見ても地球上だと同じ形の月が見えるらしい、という話になって「しまった」のですが、この事実から月と民話というテーマで話が発展するなどの副産物がありました。月に兎を見る、というのはこれは地球上ならどこでも、というわけにはいかなかったのです。アメリカでは月の見立てはむしろ三日月の時に顔を見るというほうが普通らしい、などの情報も子もたちには新鮮だったようです。さぞ豊富な伝承民話があるだろうと期待していたアラスカから、「寒いから月なんか見ない」という返事が返ってきて、私自身ずいぶんがっかりしたのを覚えています。こういうところは、大人でも十分本気でのめり込んで楽しめるのがICLNのいいところだったと思っています。
3)終戦40周年
この話をするのにアメリカとイスラエルと日本がこの前の大戦に参加していた、というのも好都合だったと思います。三者の立場が鮮明に違う、という予想された結果は、予想されていただけに感慨深いものがありました。アメリカにとっては終戦は勝ち戦さであり、良識が原爆投下の是非を問う、という構図をとります。イスラエルにとって終戦はホロコーストの終わりとして絶大な意味をもつものですから、原爆は暗黙に「どうでもいいこと」として見すごされがちでした。日本の立場は、これらに比して、どこに良識があるのか、何が終わったのか、はっきりしないということになります。
立場ははっきりしないままに、アメリカ、イスラエルと比較したとき、誰を責めるでもなく、自分が悪かったと言うでもなく、はっきりしないまま「過ちは繰り返しませぬから」という態度をとるのが日本だ、というその暖昧さが際立ってきました。比較する対象があって初めて見えてくるものを扱うためのネットワークの役割がうかがえるプロジェクトだったと思っています。
4)世界地図の中心
比較して初めてもとから見えているはずのものが見えたもう1つの意見交換として は、小学校の教室に貼ってある世界地図の「中心はどこ?」という情報交換がありました。それぞれ自分のところが中心になっているのです。つまり、日本の位置は、日本やアジアの世界地図だと図の中央、ヨーロッパの世界地図だと右の端の端、アメリ力の地図だと図の左側になります。毎日見ていれば、そこからいろいろ分かりそうなものですが、見慣れた図だけに、違う図柄がありうることに気づくのがむずかしかったのだと思います。見る立場が違えば見たいと思うものが違うことに自覚的になれるのは、けっこう貴重な体験でした。
5)女性の職業意識

日本の短期大学の学生が繰り返し取り上げたポピュラーなテーマの1つに、あなたの国では女性はいつまで勤め続けますか、という女性と職業に関する質問がありました。
このような質問を日本人に対してすると、たいていは、子どもが生まれるまでという答えが返ってきます。これに対してアメリカ人は、全員が全員ではないけれど、好きな間だけ続ける、飽きたらやめる、というような答え方をします。この答え方は、日本人の学生にとって、非常に分かりにくい答えであったようでした。笑ったりする学生もいたほどです。思いがけない考え方であったのかもしれません。けれど、そのような答えをなぜアメリカの学生がするのかということをもう1回真面目に考え直してみることで、もともと職業というものに対する考え方がアメリカの学生と日本の学生で違うのではないかということに気がついていったグループもありました。
日本の場合、大学を卒業したらみんな就職します。大学を卒業したらしなければいけないことの1つが就職なのです。その場合、就職をする、職を得るということが大切で、どのような職につくかは必ずしも学生の思いどおりにはならないという現実があります。実際、大企業に入って、営業の仕事に就くということがある程度予測ができたとしても、ずっと営業にいるのかどうかは分からないし、第1、営業というところで何をするのかも分かりません。このような状況では、飽きたらやめる、という発想はなかなか立ちにくかったのだと思います。
むしろありうるのは、周りの人がやめるときにやめるというような話になるでしょう。そこで世の中の、女の人がどのくらい勤め続けるのかを考えてみれば、まあ妥当な線が子どもが生まれるまでかなというようなことになって、日本人の回答ができ上がっていたのではないでしょうか。そうではなくて、実際いつまで勤め続けるつもりですかと言われたら、これは自分が好きな仕事に就いているのであればあるだけ、飽きたらやめる、飽きるまで自分は続けるのだ、という答えができるということになるでしょう。こんな微妙な答え方の違いに気づくのは簡単なことではありませんが、こういう気付きから、日本の学生たちは、就職は自分のためにするものだ、という原点に立ち戻って考えることができたようです。
この学生たちは、イスラエルの学生に対しても同じ質問をしました。イスラエルの学生からは、私たちは大学を出た後2年間兵役に就くので、今のところどこへ就職するか、就職して何年勤め続けるかというようなことは考えていません、という返事が返ってきました。このようなあからさまな違いというのは、知識としては大事ですが、逆にそこから先、何をどう考えていったらいいのかむずかしい面もあります。
日本人の学生にとって、自分たちが兵役に就かなければならないとしたら、どのように考え方が変わるだろうか、ということは、そもそも考え始めることが困難でしょう。一見すると、文化の違いを明らかにした答えのほうが学生たちの考え方を変えていきそうに見えますが、そうとばかりも言えません。飽きたらやめる、というような、始めは半分冗談にしか見えないような答えによって、どうしてこんな答えが出てくるんだろう、と考えてみるきっかけさえ与えられれば、そこから自分たちがあたりまえだと思っていたことへの見直しが導き出される可能性もあるでしょう。このようなことがあるから、ネットワークを学びのなかで使っていこうという場合、その学びの場を構成する教師と学生の柔軟性が大切になってくると思います。
6)学校をよくする
「アイディア募ります。アイディアを交換して、他の人達のアイディアから学び、みんなで学校をよくしましょう」というプロジェクトでした。こういう一見うまくいきそうなプロジェクトが、うまくいかないのです。学校をよくすることができる、という実感が持ちにくいということもあるでしょう。他の国でうまくいっているからといって自分のところに応用できるはずがないと最初に感じてしまうところが、学生の参加を抑制してもいたようでした。うまくいけばすごくおもしろそう、だけでは学生はたぶん動きません。現実味が必要なのだと思います。
7)自 立
「目立とは何か」という日本人学生の質問に、アメリカやロシアの学生、先生がずいぶん苦労しながら答えてくれたプロジェクトでした。「あなたは人と違うことをするのが平気ですか」というような質問は、アメリカ人には奇異に聞こえるし、どう答えていいか分かりにくいようです。それで答えが返ってきません。答えが返ってこないとき、答えが返ってこないこと自体をどう解釈したらいいのかで学生が考えこみます。そんな繰り返しから学生がずいぶんとものを考えたプロジェクトでもありました。意見交換のなかで、「自分の好きなことをする/好きなことができる」のが自立ではなく、「自分で好きなことをしてよい」というコントロール権を受け取るだけの認められ方をすることが自立につながる、という複雑な議論が繰り返しなされました。日本の学生は、こういうやり取りを通して、初期の「自分で自分の世話ができること(たとえば朝自分で起きる)」といった自立の説明から、1年半をかけて、「目立とは、他人が自分とは違うということを認めることを前提として、互いの違いを尊重すること」という結論に達していきました。
8)文化紹介パッケージ
言葉だけでは伝わらない、というときには郵送での写真の送り合いなども試みました。ネットでの応答の手軽さと速度に比べると実物の郵送はいかにも重いのです。よさそうで、長続きはしなかった、というのが私の印象です。
9)国際ニュース比較
交換したのは新聞1面に出た国際ニュースの見出しです。国際ニュースは、本当の国際ではない、という結論が出ました。イスラエルやアメリカの新聞には韓国の話題は載らないのです。情報のなかには、待っていただけでは手に入れられないものがあります。今なら、ウェブを使えば手に入りやすいという直観が働くことでしょう。
10)値段比べ
「日本は高い!」という「教育」にも使えますが、純粋にポンド、ドル、円の換算練習用の教材とか、比と割合が、元にする量の違いで異なった値になることの直観的な理解を助けるための教材など、利用価値の高いデータが手にはいるプロジェクトでした。副産物として、小学生から、「日本から見るとアルゼンチンは値段が安いですが、アルゼンチンの人から見てアルゼンチンの食費は安いのですか?」という質問が出ました。こういう相対的なものの見方を、この小学生はどこで身につけたのでしょうか? ネットの上での値段の比較という活動そのものがこのような相対的な視点転換を可能にしたのだとしたら、これもネットワーク活動の効果として注目に値するものでしょう。
11)ホームレス
社会問題は、取り上げやすいけれど、ある地域での社会問題が、他の地域でも共有されていることはむしろ少ないのです。「飲み水はどこからくるのか」といった、一見のんびりした問いへの答えが地域差、社会機能差を浮き彫りにできたのに対して、10年前に取り上げられたこのテーマは、十分成熟しませんでした。日本の学生にとってホームレスという現象そのものがほとんど視野に入っていなかったためです。
12)ことわざ比べ
文字通り、ことわざを訳してやり取りしようというものです。
よさそうで、やるべきこともはっきりしていて、ある程度活動したな、というとこるまではいきました。けれど、作業量が多かったわりにうまくいったという実感がわきませんでした。異文化に、自分たちのものと同じことわざがあれば「人はどこでもみな同じようなことを考えるのね」ということになってしまうし、違うことわざがあれば「へえ、ずいぶん違うのね」で終わってしまって、それ以上何をどう考えたらいいのかが把みにくかったせいではないかと思います。
「やったほうがよさそうなこと」と「やらないほうがよさそうなこと」

ICLNのプロジェクトに参加してみて思ったことは、最初に直観として感じていたことは、それほど根拠のあるものではなかったけれど、相当正しかったのではないかということです。単なる情報のやり取りではだめで、「何のために、何が知りたいのか」が少なくともどこかの人たちにははじめからはっきりしているプロジェクトでないと、一見おもしろそうでも長続きしないこと、大事なのはやり取りの回数やデータの量ではなく、もらったデータを生かせるアイディアや、そこから触発される考え方の変化だということ、そういう意味ではオン・ラインのやり取りよりもオフ・ラインでのそれぞれの教室での活動がネットワークの生死を決めるくらい大事だということなどです。だからこそ、データをもらうだけでなく、どんなに時間があいてしまってからでも、「いただいたデータをもとに私たちはこんなことをしました、考えました」という事後報告が大事だというのも、その当時ICLNに関わっていたみんなの共通認識でした。
予想していなかったのは(可能性としては予想されたことですが)、そこで情報がやり取りされるだけでなく、やり取りするための情報がそこに溜まってきて、初めてネットワーク自体がこれだけ複雑多岐で雑多なデータベースに実際なるのだということと、その普及の速さです。
インターネットの、データベースとしての性格がはっきりしてくるにつれて、そこに見て取られる「教育的価値」も変わってきて、情報があるだけでよいという見方もあるのだろうと思います。しかし、ネットワークである以上、そこで一方的に情報が受け取られたり、出て行ったりするだけではもったいないものです。上のプロジェクトを概観して見えてくるのは、比較がうまく働いて、比較の結果それまであたりまえすぎていたり、速すぎたりして気づかなかった観点があらわになってくるとき、考えるという活動に火がつくらしい、ということです。
そういう比較をうまく働かせるために、「やったほうがよさそうなこと」としては、まず「知りたいことは何なのか、それをはっきりさせること」であるようです。はっきりさせるのに自分たちのことからまず調べてみる必要のあることが多くなります。「こちらはこう、そちらは?」「私たちはこう考えます。こういう理由があるからです。で、そちらは?」という問いがきちんと成り立ってからのほうが、相手の答えが生きてきます。プロジェクトベース、問題ベースのデータ交換のほうが1般にうまくいくようです。
これに対して、ネットワークは単なるコミュニケーションの道具ですから「やらないほうがよさそうなこと」というのは考えにくいのですが、敢えていうなら、「一方的に自分のことを相手(それも不特定多数の相手)に伝える」というタイプの活動は、それに偶然興味をもって応答してくれる人がいるとか、同好の土が集まるとかいう幸運にめぐまれない限り、あまりうまくいかないのではないかと思います。自己紹介型のプロジェクトの1番の問題点は、はじめ(たとえば1年目)はいいのですが、何度も繰り返しているうちに先生のほうが飽きてしまうことです。飽きてしまうようならなにもネットを使い続ける必要はない、ということになります。
結局どこかで、ネットが生きるか死ぬかを決めているのは、「知りたいこと」「知らせたいこと」「私はこう思うんだけどあなたは?」というコミュニケーションのニーズがあることなのではないかと思います。
日本でも今、100校プロジェクト、こねっとプラン、キッズネット、メディアキッズなどなどさまざまなプロジェクトが動き出しています。それらのプロジェクトのなかで成功や失敗が積み重ねられて、ここに書いたような私たちの直観と、いくばくかの経験から得た知恵が淘汰されて、本物になっていくといいと願っています。
2.北米で今起きていること

教育は、1つの学校、1つの教室、1人の先生ができることではなくなってきています。教室という壁に囲まれた世界、学校という特殊な日常状況のなかで通用するだけではない学びを目指した場合には、特にそうであるように思います。先生1人では社会を代表することができません。先生1人では、たくさんの生徒たちのいろいろな興味、関心に応じた対応をすることがむずかしいのです。教師が1人で対処できるのは、自分と同じような研究テーマと方法でこれから研究者の仲間入りをしようという大学院レベルの学生を、その学生も受け入れてくれるという幸運が支えてくれるという場合に限り、親身になって指導できる、というケースくらいなものでしょう。
だから、最近の教育実践研究の多くは、たくさんの研究者が協調的に仕事をしている共同研究が多くなっています。第4章に紹介したCSCLでも、ほとんどの発表が何らかの大型プロジェクトに関連しています。
ここでは、ネットワークの教育利用の現状を少しだけ紹介する意味で、北米でのそれらの大型プロジェクトのいくつかに触れることにします。これらのいずれも、ここ2、3年のうちに総括的な報告書が本の形で出てくることが期待されています。しかも、ネットワーク上で触れてみることのできるプロジェクトがほとんどです。これらすべてが現在活動中のものであり、子どもたちの活動に即応して、ソフトが作り替えられたり、課題がより洗練されたり、参加するクラスや学校が増えたり減ったりしながら日々変化しています。こういうものは、詳細に追いかけて「見て報告」すればいいというものではないでしょう。私たちは、いずれ何かを教えているか、学んでいるか、そのどちらかだという意味で、私たち自身が実践者なのですから、こういうことはできる範囲で自分でもやってみるべきものだろうと思います。だから、ここでの紹介はほんとうに簡単に、こういうことができるのだ、やられているのだ、という紹介に留めておきます。
1)<Co Vis Project――高校レベルの地球・環境科学>
ノースウェスタン大学学習科学研究所のエデルソン、ピー、ゴメスらを中心とした、ネットワークによる遠隔地協調型の学習プロジェクトです。典型的な発見型の学習を強調していて、「ここまで学べばいい」という目標を設けていません。拠り所にしている考え方としては次のようなものがあります。
- ・目的を持って自分から学ぶときに最大の学びができる。
- ・知っていること、分かっていることの違う人々が協調して、それぞれ異なる見方を持ち込んでゴールを達成しようとする経験を積むことで、1人では学べない範囲のことを学ぶことができる。
- ・互いに自分の知っていること、分かっていることを伝達し合う必要から、知っていることの整理と知らないことの確認ができる。
このプロジェクトでは、Collaboratory Notebookというソフトを使って学習を支援しています。ノートには、「質問」「思いついた答」「思いついた答が正しい証拠」「思いついた答の反例」「調べ方」「調べるためにすること」「情報」「コメント」を書く欄があります。ここに書き込まれた内容は、生徒たちが互いにリンクを張って参照できるようになっています。
このようなノートをプロジェクトに参加しているみんなが使えることで、友だち同士の教え合いが活発になるほか、先生が生徒の活動にコメントするなどの形で参加しやすくなり、先生と生徒の間のインタラクションが取りやすくなると報告されています。
具体例としては、あるクラスの生徒たちの1グループがネット上の気象データを利用して自分たちで天気予報を始めたところ、それを先生がクラス全体での天気予報プロジェクトに仕立て上げたという話があります。参加した生徒たちのグループ間では天気の予想だけでなく、予想の根拠についてのやり取りが活発になされて、全体でより正確な予報の方法についての考えが深められたという例が報告されています。現在このプロジェクトには、アメリカの40以上の学校で数千人の学生が参加しており、参加レベルは高等学校から大学学部、大学院に広がっています。
2)<KIE――小学校高学年から中学校レベルの理科教育>

カリフォルニア大学バークレー校のマーシャ・リンを中心とするプロジェクトです。10歳から14歳の生徒400人以上に使われているそうです。理科教育の一環として、生徒自身が、いくつもの情報源から得られる情報をエキスパートの助けを得て自分で統合していくことを活動の中心に置いています。生徒たちは、いくつか提示されるテーマのなかから自分の興味に合うものを選び、日常生活での自分の体験、実験から分かったこと、本や新聞、雑誌、テレビなどから調べたこと、ネットから得た情報のすべてを加えて「自分の考え」を作ります。このような経験を通して、生徒が世の中にある情報のなかから正しい情報を選んで有効に利用できるようになること、言い換えれば信頼できる情報とそうでない情報、必要な情報とそうでない情報を区別して扱う方法を身につけさせることを1つの大きな目標としています。また、このような活動を通して、生徒たちが自分たちの日常的な生活と学校で学ぶ知識とを自分から結び付けるようになることも狙いの1つだと言われています。
KIEには、生徒たちの
- ・自分の考えから理論をたてること
- ・暖味な根拠としっかりした根拠を区別すること
- ・分かったことを、世の中で実際に問題にされている大きな問題の解決に役立てること
のような活動をサポートするための仕掛けがソフトウェアとして組み込まれています。のSpeakEasyという討論を整理するためのツールを使って、生徒たちは、先生や、ネット上で協力してくれる科学の専門家の人たちと、決まったテーマについて、現在認められている考え方にどんなものがあるか、どのような証拠がそれらの考え方を支持しているか、または反証になっているか、などを整理していきます。
証拠は、ネットの上から探して来てもいいのですが、協力してくれている科学者からも提供されます。「光はどのくらい遠くまでとどくでしょう?」というプロジェクトでは、サーチライトが空まで届いている(けれど、遠くのほうではたしかに手元より光が弱まっているように見える)同じ写真が、「光はどこまでもずっと進んで行く」と考えている子どもたちにとっても、反対に「光は遠くに行くほど弱くなっていつかは消えてしまう」と考えている子どもたちにとっても、自分たちの考えを支持する証拠として挙げられて、両方のグループの子どもたちがびっくりする、などの具体的な経験を通して、子どもたちは仮説を立てることのおもしろさ、立てた仮説の正しさを説得的に証明することのむずかしさなどを学んでいく、と報告されています。
3)<CSILE――協調、理解中心複合カリキュラム>
トロント大学教育研究所マーレーヌ・スカルダマリア、カール・ベライターらを中心とした、認知科学的な豊富な教育方法研究に裏打ちされたプロジェクトです。自分の考えを友達に説明することで考えを深めていく、という基本的なアプローチをとっています。ソフトウェアは、そのための支援であり、「知識はみんなで作り上げていくもの」だと考えられています。 CSILEでも、一定のフォーマットに従ったデータベースが作られます。それぞれの参加者が、「問題」「私の考える答」「分かりたいこと、知らなくてはならないこと」「新しく分かったこと」などの項目を分けて、自分たちで実験したり調べたりして分かったことをデータベースに書き込んでいきます。それらをみんなに見やすく提供することで、生徒たちは自分たち自身で、いろいろな考え方があることを知ってさらに問題を探り出したり、他の人と意見の違うところを見つけて議論したりします。こういう他の人とのやり取りのなかから、1人1人が自分の知りたいことを確かめ、みんなの知りたいことの答えを積み上げていく「知識の共同体」ができるのだ、とされています。
開発、実践とその評価にすでに10年近い年月がかけられており、六歳から大学生までトロント大学を中心とした地域の研究校で日常的に使われています。遠隔地との共同学習の実験も、現在4ヵ国をつないで行われています。教科を問わず実践されていますが、成果としては、「大事なことは、生徒たちがものごとを深く理解するようになることだけでなく、深く理解するにはどうしたらいいかを身につけることだ」と報告されています。
4)<ALN――全カナダネットワーク利用通信教育型大学>

大学レベルでの遠隔教育プロジェクトは、大型のものがいくつも試験的に開発、実施されていますが、これはそういったものの1 つで、ウェブ(インターネット)、電子メイル、ニュースネットにビデオ教材、従来型の紙教材を組み合わせた完全ネットワーク対応型の非同期大学学部教育プロジェクトです。非同期とはいっても、ネットニュースを利用しての議論や、生徒が何人かで1緒にプロジェクトをやる機会などが組み込まれているもので、生徒が自宅から大学にアクセスすると、まず最初にその生徒に合わせたプロジェクトの進行表や行事の予定表、課題の進み具合についての評価などが表示されるなど、生徒の活動管理に細かな配慮がなされています。効率的な実施には教師の側の負担の分散、カリキュラムの組み方の慣れも大切であることが分かってきているといいます。
特に、他の遠隔教育プログラムでもかなり言われるようになってきていることとして、この教師の負担増の問題があります。私たちも日常的にネットを大学の講義に運動させて利用していて感じることですが、学生の質問にはできるだけ早く返事を書いてあげたいと思うだけで、学生がたくさんいたらどんな事態が起きうるか想像がつかれると思います。より現実的には、課題提出の締切直前の五分間に何十人もがわっと大きなファイルを送ってきて回線がパンクしてしまうのをどうするか、などとにかく解決しなければならない問題も頻発します。地味な努力が必要とされる実践ですが、少し遠い将来必ず起きるであろう教育の形の変化にそなえるために、今から知恵を出し合っておく必要がありそうです。
ここ2、3年、これらのプロジェクトをまとめて紹介・解説した本が続けざまに出版されています。どれも、紹介としては役に立ちますが、詳しいカリキュラムとか、子どもたちの活動の実際とか、評価の方法、使われているソフトウェアの詳細など詳しいことまでは触れられていません。詳しく書こうとすると書くべきことが多すぎる、という面もあるかもしれませんが、それ以上にそれらの雑多な事実が適度なまとまりを生むほどには経験が熟していないのではないかという気もします。それぞれ10年越しのプロジェクトといったものが多いのですが、そういう意味でもここはまだ若い研究領域なのだろうと思います。
成果が出てくるのはこれからであり、その成果を少しでも私たち1人1人が望んでいるような方向にもっていくためには、まず私たち1人1人がそういう活動に参加して、何を望んでいるのかをはっきりさせることから始めてみるのが自然な態度なのではないか、という気がしています。