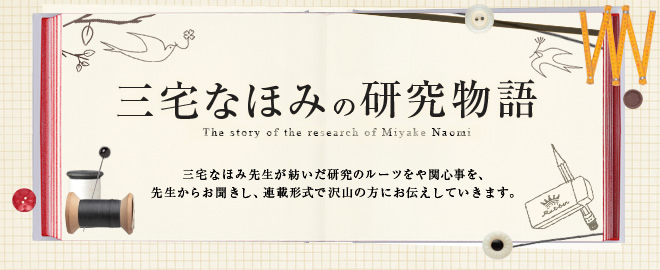―― 三宅芳雄 先生に出会ったのは、大学院に入ってからのことですか?

三宅
もう少し、前でしたね。4年生の頃に、実は会っています。あの頃、大学間セミナーというのがあって、八王子のセミナーハウスという所に複数の大学から学生が集まるというようなことがあったんですよ。3~4日間のサマースクールみたいなものですね。「情報処理心理学の動向」といったようなテーマごとに、20人くらいの学生がバンガローに泊まって、全体の討論会などがありました。そこでは、文化人類学や発達を研究していらした原ひろ子 先生にも出会いました。とても力のこもった講義でした。ああ、こういう女性研究者がいたのか、と思ったりしました。
東大の大学院に行ってみたら、そこで出会った方々が、皆いたんですよ。同じセクションに出ていたんです。情報処理系の新しい認知心理学という、実際に人の認知行動を説明できるモデルを作って確かめようというアプローチでしたね。八王子ではそんな考え方を高田洋一郎先生という方から伺いました。それで、各グループでディスカッションした後には、最後には全体発表会があったんですよ。先生がまとめるのではなくて、学生がそれぞれのテーマで考えたことを話してよね、というクロストークのようなね。その場でいろんな人がいろいろ発表するので、おもしろいなと思ったのを覚えていますね。で、なぜか情報処理なんてなんにもわかってなくて、東大勢が議論を引っ張っていたはずなのになぜかその話し合いの結果を最後の全体会で私が発表することになってしまって、「なんで私が?」ってかなり焦ったことなんかを覚えてますね。じゃんけんで負けたのかな?
その頃、同時に、実験室の中で起きたことをデータにして法則を見つけ出すよりは、それまで実験室で扱ってきた現象を日常生活の中で調べたらどれほどの差があるか、その違いをどうやって説明するか、などを問題にする人たちが認知心理学研究者のなかにも出て来ていたのですね。今聞くと、「状況論?」って思うかもしれないけど、1960年代の半ばころからね、現象のEcological validity、生態学的妥当性 を問題にする、という考え方がNeisserを中心に出ていました。 人の心理を研究するなら、それが生きて働いている場でecologicalに validな研究をしていかなくてはいけないね、という考え方があって、それには私たちも随分共感していろいろ議論したりしました。
当時は、学校に行ったら1クラス50数名いるっていうような時代でしょ?だから、先生にあまり頼れない雰囲気がありました。人数が多いのでどうしても先生からも目こぼれしてしまう。そういう世代だったんですね。
後から思えば、その同級生の8名は、ものすごく積極的なのがそろっていましたね。集まっては何か自分たちでやっていた、という学年でした。2人は臨床系だったので少し距離があったのですけれど。あとの6人は、誰かが本を持ってきて「この本を読む勉強会をやろう」とか、1年生だけでさっさと取り組み始めたりね。そんなことしてたら、先生の方が院生室までやってこられて「何の本読んでるの?」なんて聞いて下さったりね、そんな勢いでした。すごく積極的なグループだったんですね。
そこに、波多野先生がお兄さんのような存在で、波多野セミナーというようなことをされていました。そこは、呼ばれないと参加できないというような雰囲気だったんですけれど、私たちの仲間が参加して、人数がどーっと増えました。
そこで、最初にドクターの発表なんかを聞いていましたところ、どうもわからないな、と思ったことがありました。内部進学の人が多いから、他の人はこれまでの発表や経緯も知っていてわかっているのだろうけれど、私にはわからなかったので、「これは困ったな」と思いました。誰も、質問しないんですよ。
それで、やっぱり、知らないから聞けるというのもあるじゃない?だから、「1年生で、初めてお聞きするからわからなくて質問するのですけれども、取り組んだ研究の結果がこう出ているところから、どうしてこういう結論になるのでしょうか」と質問してみたんですね。すると、その方は「あら、また言われたわ」と仰ったんです。そうすると、上級生の方たちがざわっとした感じになった。その点が多分その方の研究でちょっと弱いところで、みんな知っているからそこは聞かなかったんだけれど、それを何も知らずに素直に聞いちゃった、というので、私、一躍有名になってしまったんですね・・・。