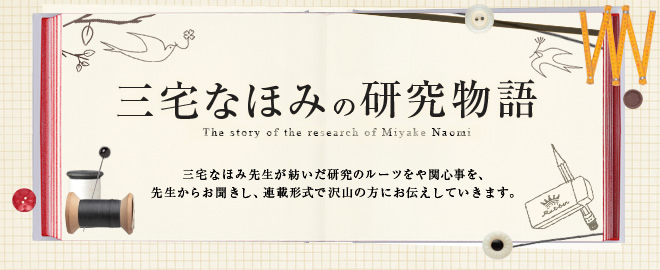―― やがて進路を決める時期がやってくるわけですが、すんなりと決まったんですか?
三宅
最初、私は、卒論の指導をこの春日さんにお願いしたいと思っていたのね。先生の部屋にはたくさん英語の学術誌があって、その中に、「ある講義について、先生が話す音声のみ音声に講義内容のテキストを加えたもの、音声と講義内容テキストにさらに講義の映像も加えたもの、と追加していくと、情報が増えるから理解度が上がりそうなものだけれど、実際授業から学生が何を掴んだかを調べると案外そうでもなくて特に映像をつけると理解ががくんと落ちる」というような研究が載っていたりしてね、読んでみておもしろいなぁと思いました。1時間ほどの講義を対象にしただけの実験だったと思うんだけれど、その頃はいわゆる知覚系とか実験室の中で実験のために作った課題をやるような実験の話が多かったので、新鮮な感じがしたんです。授業の場で実証するというところがリアルな感じがしたんでしょうね。でも、春日さんにそうお伝えしたら、「自分は臨床家なので、あなたがこのまま日本でアカデミアに残っていくなら、藤永先生の所にゆくべきだよ」とアドバイスを頂きました。
―― そのときすでに、アカデミアに行くと決めていたのですか?
三宅
そこまでではないと思うんだけれど、大学院に行くことは何となく考えて、相談はしていました。留学するか、2社くらいの就職先と、大学院への進学を候補に、進路を考えていたの。私は留学に大変興味があったのですけれど、基本的には親が賛成ではなかったということがありました。それが、ある朝起きたら、勉強机に父からの手紙があったんです。「女性なんだから、何を続けるかを決めるまでは、勉強を続けるのもいいのではないか。それをサポートするだけの余裕と、意志はあるから」と。「進学するにしても、まだ日本がいいんじゃないか。日本でどこに行くかはお前に任せる」と。
―― すばらしい。お父様も、アカデミアなのですか?
三宅
後から考えると、両親ともそういうことをしたかったかもしれないですね。父は三男で、大学を出て銀行に勤めていましたし、母はもう少し進学したいときに、事情が許さなかったりしましたからね。
―― そういう時代というのもありますからね、やりたいことをやらせてあげたい、ということがあったんですね。しかし、一緒に住んでいてお手紙、というのもおもしろいですね。
三宅

ことばに強い父親でもありましたからね。一応それでも奨学金への応募も考えたのですが、最終選考で残念だったり、親にも反対にあったりして。
当時、お茶の水女子大学は修士課程までしかなくて、博士課程がなかったんです。博士課程がそのうちできると聞いてはいたのですが、なかなか気配が見えなくてね。その10年前は、修士課程もなかったので、研究者になる人は修士の段階から東大にチャレンジしたんですよね。私の前に東京大学に行った人は高橋恵子 さんがいましたね。10年も前です。
しかし東京女子大学にも修士課程がなかったので、志ある人はどんどん東大に行っていたんですよ。
吉田さんと春日さんは、海外から帰ってきて東大にいらしたので、こうした様子をご存知だったんですね。それで、お2人から「行くなら、東大に行けば」と言われましたね。
どうせ博士課程までいくなら、東大に行っておいたほうがいい、ということでした。
それもあって、先輩の高橋恵子さんに相談したら、1つ上の東京女子大学から東大の修士課程に進んだ先輩を紹介していただいたんです。その1サイクル上くらいに稲垣佳世子 さんがいたんですわね。
そのような経緯で、受けてみようかという話になったわけです。それで、紹介して頂いたのがピアジェ研究でたくさん仕事をしていらっしゃる大浜幾久子さん。大浜さんから、過去問を見せて頂いたり、出題傾向を教えて頂いたりしてなんとか受験しました。
それで、試験を受けたときに4人の募集に10人が受けていました。外部から2人、内部での再チャレンジという方もいたりしてね。博士課程に進める人は、4人だったのですが。
点数が団子だったので、切れなかったらしく、実際には8人通ってしまったんですね。
その中に三宅芳雄 がいたんです。
―― 段々と、先生の現在を形作るメンバーがそろってきたわけですね。