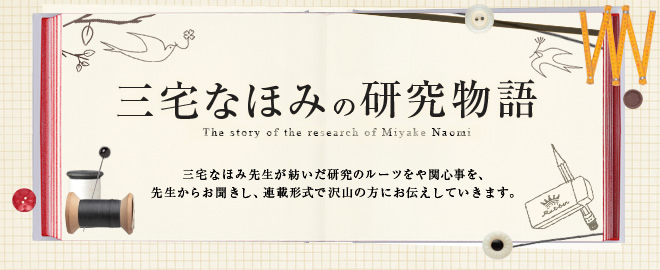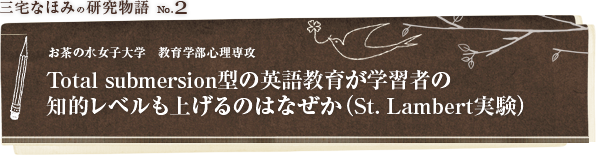

―― 入れ子型の構想の後に興味をもたれたのが、Total submersion型という英語教育についてなんですね。 このお話には、どういう風に出会われたんですか?
三宅
大学3年生くらいのときに、現象学の吉田章宏さんと当時は実験心理学という臨床系をやっていた春日喬さんが、お茶の水女子大学に移ってこられたのです。彼らに、そういうのが流行りだよ、と教えて頂いたんですね。彼らの研究室にはそういう魅力的な雑誌がたくさんあったの。知覚だけじゃなくて問題解決とか、マルティメディア・エデュケーションとか。英語ってそれまで、その、教科じゃない。
―― ええ。学校で勉強する1つの科目、という感じですね。
三宅
ええ。だから、当時は教科書ではなくて「生きて使われている英語」がおもしろかった。お2人は英語がお上手だったので、遊びに行っている間に、英語を教えて頂いたこともありました。たしか、A4用紙に1枚くらいの英語を書いて行くと添削してくれましたね。日本に帰国したばかりで、ある程度時間を取ることができたのでしょうね。
―― ところで、先生にとってこの時期は、「英語を学ぶ」ことや「日本語で学ぶ」ことを比べたり、考えたりしていた時期なのでしょうか?
これは、すごく後付けの説明かもしれませんが・・・。数年前に提出したレポートを後で見たり、小さい頃に書いた日記を読んだりして、おもしろいと感じることはありましたね。 過去に自分が書いたものを見るとか、自分の言い方と友達の言い方を対比して物を見ることがおもしろい、ということがあったと思いますね。
もう1つは、大学では第二外国語としてフランス語を習っていました。随分一生懸命いろいろやってみたけれど、全然だめなの。英語はなんとか書けていたんですけどね。 どこかで、サピア=ウォーフみたいな、「ことばが違うと考え方が違う」という話が好きだったかもしれないですね。
その頃、日本で行われている英語教育の形というのは、日本語で授業を行うのが一般的でしたが、授業空間全体を別の言語にしてしまうというものの、はしりがあったんです。その頃興味を持っていたTotal Submersionというのがそれで、カナダのケベック州で60年代に始まったプログラムだったんですね。
最初はフランス領の人たちが、英語をできるようになるといいというのでやっていたのですが、英語は支配者層のことばですから、それはまずいということになって、結局は逆をやったんですね。つまり、フランス語ですべてを教える学校に、英語圏の子どもを募ったんです。それが、セントランバートという所です。これはたぶん、波多野誼余夫 さん経由で知ったのだと思います。
波多野誼余夫(1935-2006)
認知科学に限らず、国内外の多くの心理学者に影響を与え続けた認知科学会の巨匠。
研究成果は国際学会に発表し続けると共に、国内では一般書も数多く出版した。
博士(東京大学・教育学)。
著書に、稲垣佳世子と共著で「知力の発達」「知力と学力」(岩波新書)、「知的好奇心」「無気力の心理学」「人はいかに学ぶか」(中公新書)。
「認知心理学口座4.学習と発達」「音楽と認知」(東京大学出版会)等多数。