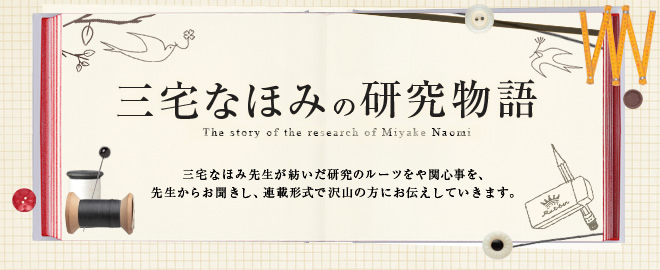――先生が修士論文を出し終えた頃でしょうか、ICPという学会が開かれたんですね?

三宅
ICPはInternational Congress of Psychology 、国際心理学会と訳されるんですが、ほとんどヨーロッパベースの心理学会です。アメリカはまた別に、独自のAPA(American Psychological Association)がありますが、ヨーロッパは歴史が長いこともあって、当時はICPの方が中心的な存在だったんですね。いまだに4年に1回は開かれています。 そのICPという学会を、東洋先生が、アジアで初めて日本に持ってきて開催にこぎつけたという経緯でした。 私が修士2年の時。1972年のことです。
当時、日本政府から予算を取り、東先生は事務局長として駆け回っていらっしゃいましたね。私は彼の事務局長付きの、秘書でした。ティータイムをセットしておくとか、届け物をするとか、東先生を尋ねて来られる海外の方の受付をするとか。東先生のところに完全常駐のベテランの秘書さんがいたので、その方を手伝っていました。彼女と参加者名簿を作ったのですけど、変わった綴りのお名前が多くて、読み合わせようとしてもうまく発音できないから、二人で笑い転げたりしてたと思います。
こういう風に小さな仕事がいろいろあったんだけれど、そんなに忙しかった覚えはないですね。当時、心理学をやっていた人は、いろいろな所で何らかの形で関わったと思います。 波多野先生が文房具の買い出しやってらしたりね。
――アジアで初めて開催された学会で、ノーマン 先生とお会いになった、ということですね。
三宅
そうですね。そこで初めて出会ったと思います。学生は各自が仕事を分担して、空き時間には聴講していいことになっていたので、そうやって参加したセッションのひとつでした。
――ノーマン先生は当時、どういうご様子だったのでしょうか?
三宅
なんだか、全然立ち止っていない、大変にアクティブな方でしたね。
彼の主張は「リアルな人間が本当にやることから見て、正しい人間のとらえ方をすべきだ」ということでした。「普通の人が日常的に行うことの文脈の中で現実的なプロセスを研究しなければ、ものはわかってこない。実験を目的に、例えば人間のリアリティから離れた無意味つづりの記憶を法則化しても、ほとんど意味がない」と主張したわけです。当事、70年代の初めにね。
ナイサーのEcological Validity論争の元になる本の出版が1976年ですから、当時はこうしたことが盛んに言われつつあった。 元来、ノーマンは工学部を卒業して、「物を作るなら人の心理を勉強しよう」と思って心理学の大学院に入ったんです。そこで短期記憶を研究している先生と一緒に論文を書いたりしていらした。
被験者の記憶をテストする記憶研究がありますね。例えば、項目がたくさん並んだリストを覚えてもらって、その中に「こういう項目ががあったか」「何番目にあったか」といったことを被験者に判断してもらったりね。質問してから答えるまでに一番時間がかかるのは、最初からリストに入ってなかったものについて尋ねたときです。リストの最 初から最後まで全部当たらないと、わからないですから、時間がかかるんですね。
彼は、正当な反応時間差には、人が日常的に覚えていることが絶対に関係する、と主張しました。今は、携帯電話の時代ですからみんな携帯見て電話かけてて、自分の番号すら覚えてなかったりすると思いますけど、当時は電話番号をいくつか記憶して、それで連絡を取り合っていた時代です。必要に迫られて、自宅や事務所や知人宅など、30か40は覚えていた のではないかしら。
でね、電話番号って、日常生活の中では一番無意味つづりに近い記憶ですよね。でも「チャールズ・ディケンズの電話番号は?」と聞かれたら、記憶上のリストを操作 する時間なんて、必要ない。チャールズ・ディケンズの生きた時代、まだ電話は一般家庭になかったでしょ?だから、そう聞かれたら、普通なら即座に「その時代、電話まだないだろ?」って答えるでしょう。つまりノーマンは、そういう例を出して、別の理由で、チャールズ・ディケンズの電話番号が自分のリストにあるかどうかという判断がつくだろう、そういう人の判断の仕方も説明できる記憶研究じゃないと意味がないだろうと言ったんですね。
人のリアリティってそういうものですよね。だから、私は人間のリアリティに迫るダン・ノーマンという研究者を「おもしろい」と思いました。
彼の振る舞いや話す様子を見ているとペースが速いし、指導教官にしたらきっと大変だろうと思いましたけれど、研究内容がおもしろいと思ったんです。とはいえ、初めに「米国に行くならこの人」と言い出したのは、連れ合いのほうなんですけどね。
――三宅芳雄先生は、なほみ先生の人生のパートナーですけれど、ノーマンの所で研究することも、同じ時期に決断されたわけですね。