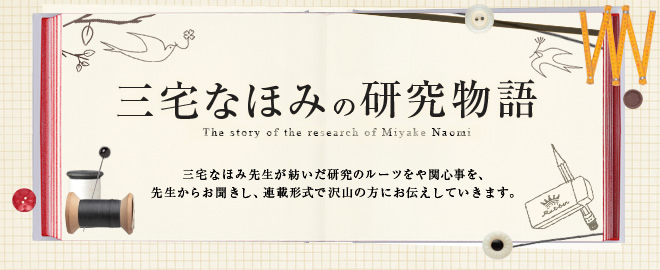――この頃、佐伯胖先生 の小人の話(擬人的認識論)に出会われたんですか?

三宅
先ほどお話したように、私がやっていることは言語の相対性みたいなことなんだけれど、一方で「多分それだけではないな」という感じもあったのね。
私が考えているのは、ことばをつかってどう考えるかという、ことばと理解の話だと思いました。話し手と聞き手の視点の違いとか、自分がどういう視点から物を見るかということが、おもしろいと思っていたんですね。
その頃の佐伯胖さんは、まさに輝ける星。教育や心理の研究を変えていく存在でした。
擬人化や、体をつかったもののわかり方について書いていたんです。「自分の分身をつかって対象を理解していく」という考えが斬新だったし、納得もさせられた感じがしていましたね。
目はここだけにあるわけではない、うまい場所に自分の分身を投げてそこから見るという話でしたが、私には、どこに分身を飛ばせばいいかわからないことが気になりました。
それを聞きに彼を訪ねて行って話をして気がついたんですが、彼は分身を飛ばせない人を相手しているわけではないようでした。たぶん、小人がいればおのずと行き先はわかるということだったのだと思います。彼のほうが状況論屋さんだということかもしれない。
私のほうは、飛ばす本体の本人が気になっていたのです。
このときに私が抱いた疑問が、留学後の修士論文(To Ask a Question, One Must Know Enough What is Not Known )につながったのだと思いますね、無理やり話をつなげると。